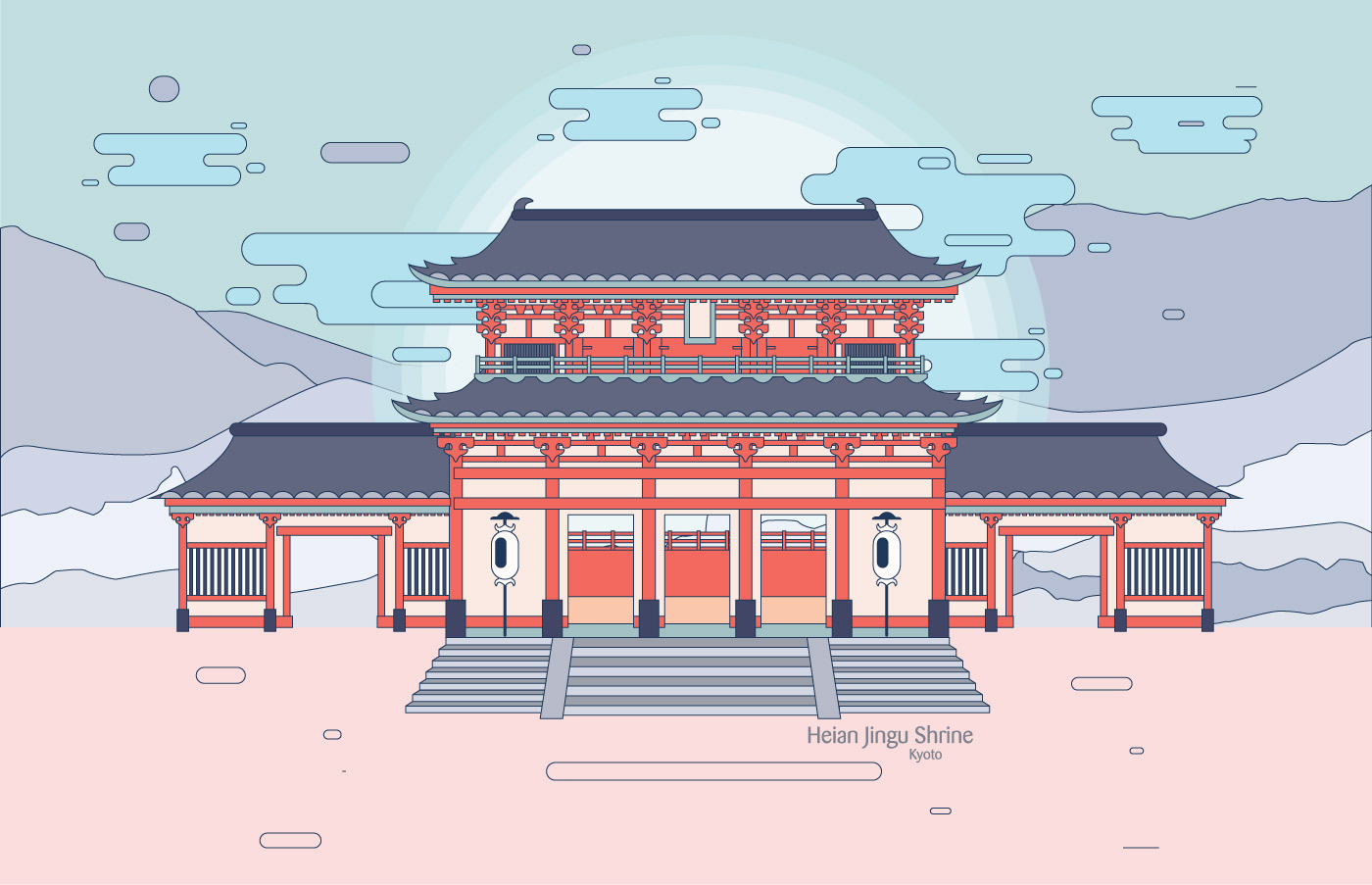䠒跪(こき)
こんばんは。
今日のお題は「䠒跪」(こき)です。
昨日の続きを読むのですが、今日の現代語訳は自信がありません!かなり厄介です。
ですから、「宿題」のタグを付けておきます。後に分かることがあれば、改善します!
是諸衆等,人各各䠒跪 ,嚴持香華,如法供養。
願此香華雲,遍滿十方界,供養一切佛・經法,並菩薩・聲聞・縁覺衆,及一切天仙。
受此香華雲,以爲光明臺,廣於無邊界。
受用作佛事,供養已,禮三寶 。
「この儀式に参加している私たちは、おのおのが、右ひざを地につけて、お香とお花を厳か(おごそか)に持ち、儀式の習わし通りに、〔三宝を〕供養いたします。
このお香とお花で作り上げた雲が、十の方角(すべての方角)に行き渡り、すべての仏さま、お経や教え、菩薩、ブッダの教えを直接お聞きになった聖者、ご自身で悟りを開いた聖者たち、また、すべての仙人に届きますように。
仏様たちは、このお香とお花の雲をお受け取りになり、それを光の台にして、さらに、無辺に広がる世界を包み込みます。
わたしは、このような仏さまがなされる場面を経験し、彼らへの供養が終わり、再び、その感動のために礼拝します。」
つまり、儀式に参加した者たちがお供養したお香やお花を、仏さまたちはお受け取りになる。そして、そのお香やお花は仏さま達の力によって、光の台となり、世界中を包み込む、という情景を儀式に参加する者達は経験します。その感動のあまり、再び、礼拝を始めるのです。
この内容は、中国の天台宗の開祖である智顗(ちぎ)という方が伝えたとされる『法華三昧懺儀』(ほっけ・ざんまい・せんぎ)というものに出る内容をかなり簡略化したもので、読みにくいです。私の和訳も検討中。
この文については、何回かに分けて見ていきましょう。
さて、今日のお題の「䠒跪」、両方とも「足へん」ですから、足にまつわるものです。インドの礼法の一つだそうです。「䠒跪」の「䠒」(こ)の「足へん」を取ると、「胡」(こ)となります。この「胡」は、中国からすると異民族や、外来種をあらわす字です。胡座(あぐら)、胡桃(くるみ、ヨーロッパ)、胡椒(こしょう)胡麻(ごま、インド発祥らしい)、胡瓜(きゅうり、インド発祥らしい)などがあります。結構あるやん!
ですから、「胡座」(あぐら)は、外国風(インドなど)の座り方。ガッテン!
では、「胡跪」(こき)の「跪」は何か?「ひざまずく」という意味です。写真見て下さい。足へんを取った「危」の字、この写真のままやん!「危」の字と、この絵を交互に見て下さい。

つまり、外国風(インド)の跪き方(ひざまずき方)が、胡跪(こき)です。
こんな感じ↓

では、また。